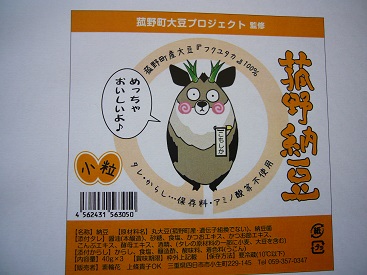小学校で地区防災学習 ~災害時や日常を「生き抜くチカラ」をはぐくむための知識や技術習得~
2025年1月18日(土) 「高花平地区防災学習」で災害時の食事についてお伝えしました。
高花平小学校は、私の母校。なんと50年程前になり自分でも驚きました。そして、こうして時を経て母校で伝える機会をいただけたことを本当に幸せに思います。 最近、校舎が立て替えられ初めて訪れたので感動箇所がいっぱい。 特に、美術の絵画が廊下や掲示板などに多数に貼ってあり、クラッシック音楽で時を知らせるタイミングもあり感動。教室も明るく広々として冷暖完備。片隅でティータイムもいいかも?と思うほど自分たちの頃とは大違いで時代の流れを感じました。(笑)
防災学習は、サイレンの後、教室から体育館に避難してくるところから始まり、学校区の自治会長・防災隊・消防団・自警団・元消防士の方々、共に力合わせての指導です。
1限目は全校生徒対象に、能登半島地震の様子・災害時のトイレの作り方・凝固剤でホントに固まるの?をペットボトルの水を使って実験。私は災害時の食事について「よく嚙んで食べる」「食事中の水分のとり方」をお話しました。


2限目は、各学年に分かれての学習
1年生 水消火器を使ったり、煙の中避難・消防車を見て大喜び
2年生 ダンボールベットの組み立て・避難所一区画スペース体験
3年生 地震体験車
4年生 防災倉庫の中を見てみよう・発電機のエンジンをかけてみよう(見学)・簡易たんかを作ってみよう(実践)
5年生 止血法・固定法・搬送法
6年生 災害時の課題を知り、必要な備えを学び、自分にできることを学び考える
私は、6年生担当で、①命を守る ②健康を保つヒント③ 過去の災害の教訓を活かす の大きく3つのテーマに分けて
支援する側として自分に何ができるかを具体的に考えてもらう機会としました。

自分の命は自分だけのものではない。大切な回りの人にとってもお互いに大事な命であることを再確認してもらい
最後は、命を守るというよりもっと直接的に「災害で死なない!」という表現で伝え、
いざという時には支援側で活躍できる人になってほしいと期待を託しました。(^^♪
「来年も」と早速お言葉をいただき、来年も訓練できることを祈ります。発災したら実践あるのみですから、訓練できる時間を大切にしたいと思います。